おはようございます☀
お父ちゃんです!
金原ひとみさんの
『YABUNONAKA』を読みました。
文芸業界を舞台に「性加害」を
複数視点で描いた500ページ越えの大作です。
読み終わってから、ずっと考えています。
▼どんな小説?
文芸誌や出版社の内部を舞台に、
・編集者
・作家
・編集者の家族
・作家の恋人
・高校生
など
10〜50代の計8人の視点が
入れ替わりながら物語は進みます。
物語は、
「10年前に編集者に性的搾取をされた」
というネットでの告発を起点に、
「性、権力、暴力、愛」が絡み合い、
各人物の正義や言い分がぶつかり合っていきます。
読者に
「誰が正しいのか」
「何が正しいのか」
を問いかけてきます。
“何が正しいか…”というよりも
考えることを投げかけてくる作品です。
・文芸業界での性加害の告発
・SNS炎上
・マッチングアプリ
・家族の断絶
まさに現代にピッタリな作品です。
▼作者が語る狙い
金原さんはこの小説について、
明確な意図を語っています。
まず「変化の記録」として書いたと。
この小説の連載が始まったのが2022年9月。
そこから2年かけて文芸誌に連載されました。
この数年で、性加害を巡る空気が変わりましたよね🤔
・海外でのMeToo運動
・旧ジャニーズ問題
・フジテレビ問題
・〇〇ハラスメント
などなど
作者の金原ひとみさんは
「時代の変化とそれに適応していく自分の感覚」
を都度書き残したかったそうです。
次に「中立的な視線」
被害者の告発本ではなく、
告発して、加害者を叩きたいのではなく、
加害者・被害者・家族・周囲の声を「俯瞰」して響かせる。
正義と悪の単純化を避けることで、
読み手の思考を促す作品設計になっています。
▼タイトルの意味
8人の章が
編集者→作家→編集者の部下→告発者→作家のパートナー→作家の娘
→編集者の息子→作家の娘→作家のパートナー→告発者→編集者の部下
→作家→編集者
と「V字」構成で反転していく特殊な並びとなっています。
視点が連鎖し、読者の判断を揺さぶります。
『YABUNONAKA』というタイトルは、
芥川龍之介の「藪の中」にならったもの。
食い違う証言と心的真実が交錯する
現代の状況を映すためのタイトルです。
「性的搾取」「性加害」と聞くと、
加害者側が圧倒的に悪いように思うけど、
本を読み進めていくと
「真相は単一ではない」
ということがわかってきます。
読み手に見極めが委ねられているんですね。
ただただ物語を読むのではなく、
考えさせられながら読み進めていきます。
金原さん自身の言葉を借りれば、
これは「変わりゆく世界を、共にサバイブしよう」という宣言。
単なる告発ではなく、
“生き延びるための思考の筋肉”
として文学を位置づける試みなんです。
『生き延びるための思考の筋肉』
この表現、個人的に好きです!
▼複数の真理がある
この小説を読んで強く感じたのは、こういうことです。
『正しいか間違っているかが問題ではない』
この世には色々な真理があります
正しい真理・間違っている真理
適切な真理・不適切な真理
その間のグレー部分も大きいです。
その中でどれだけ多くの真理に触れ、
把握できるかが重要なんじゃないかと🤔
結局のところ、私たちはどうしたって混ざり合うことのない…
混ざり合うことのできない生き物です。
いわゆる多様性です。
それぞれの正義とか、価値観ってありますが、
それはあなたの正義であり、価値観で
他人に強要すると、問題が起こります。
▼それぞれに言い分がある
それぞれに正義や価値観があるように
それぞれに言い分があります。
一方の話しか聞かず、叩くのはどうなのでしょうか?
その告発を信じて、吊し上げられるのはどうなんでしょうか?
言ったもの勝ちなところもあります。
後追いしたらしたで、言い訳などと言われる。
真実は本人にしかわかりません。
年代が違えば、生きている時代が違うし、
見えている世界も違ってきます。
後輩のことにしても、子供のことにしても、
“あーだこーだ言わない”
のが良いのかなと…🤔
逆に、年を取った時に、
若い人に教えを請えるようにしておいた方が
情報が入ってくるようにしておいた方が良いんじゃないでしょうか。
上の者からのアドバイス・求めていないアドバイスはいりません🙅
▼というわけで
『YABUNONAKA』は答えを与えない小説です。
むしろ、問いを投げかけ続け、
読者に「思考の筋肉」を求めてきます。
・複数の真理を認める
・自分の価値観や考えを押し付けない
・分かり合えないことを前提にする
・共に生きていく
この小説が教えてくれたのは、
そういうことだったのかもしれません。
この小説がないと、中々考えないことですよね🧐
良い機会を頂きました!
今日もありがとうございました🙇♂
また明日!
お父ちゃんでした👋
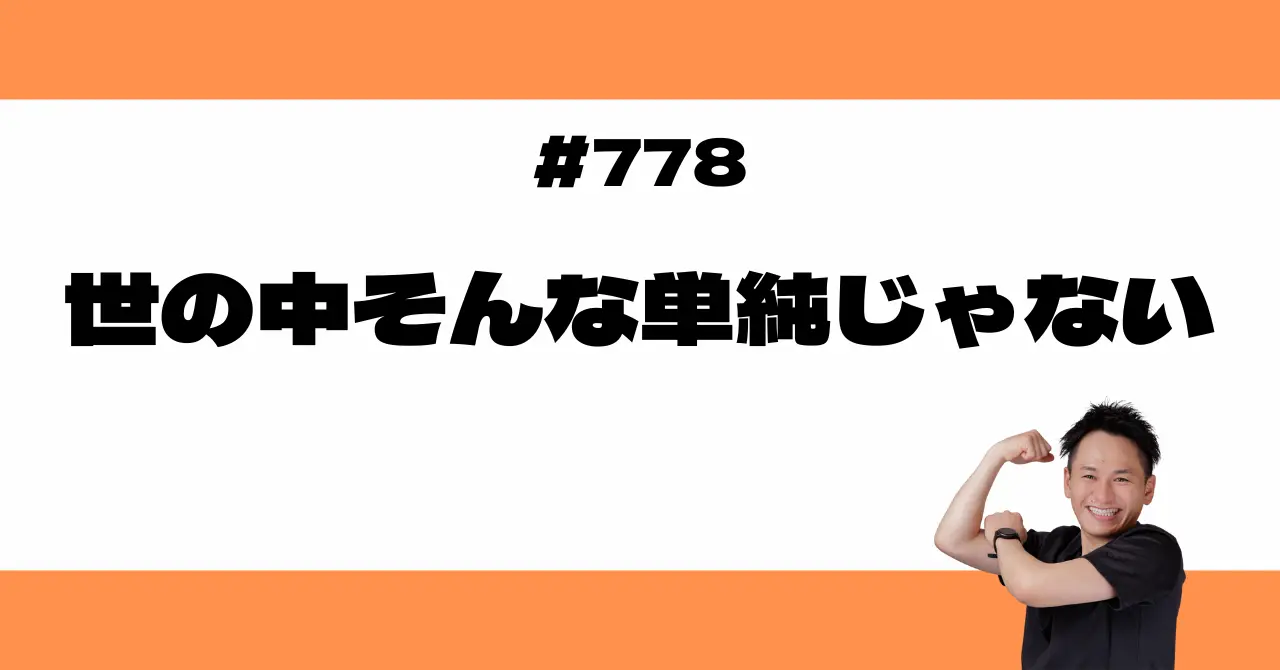
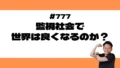
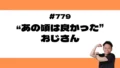
コメント