おはようございます☀
お父ちゃんです!
今日は長いので、覚悟してお読みください🫣
これでもだいぶ短くしたほうで…
元の原稿はこれの倍の量がありました。
だけど、それくらい大事な内容です。
▼平和は当たり前じゃない
「平和は当たり前ではない」
先日、万博を訪れた際にパレスチナのブースで
大学生のガイドさんからお話を聞く機会がありました。
その体験をきっかけに、パレスチナ問題について自分なりに調べてみました。
この問題は120年以上続いており、
「世界で最も解決が難しい紛争」とも呼ばれています。
そして私たちの日常が、知らず知らずのうちに
こうした争いに関わっている可能性があることを知りました。
▼パレスチナ問題の複雑さ
パレスチナ問題(パレスチナ問題に関わらず)は、
様々な要因が複雑に絡み合っています。
よく言われるのは、宗教に関する問題ですが、
「この問題は宗教の問題だけではない」
と、万博でのガイドさんも言っていました。
何か一つが解消されたからといって、急に解決する話ではありません。
そんな簡単であれば、争いなんてとっくに終わっているでしょう。
どんな要因があるのか、見ていきましょう👀
・故郷問題
・聖地 エルサレム
・地続きの恐怖
・相互の被害者意識と感情
・その他の問題
○故郷問題
パレスチナ問題の根底には、
「ユダヤ人の歴史的迫害・離散」と「パレスチナ人の故郷喪失」
という2つの悲劇があります。
・ユダヤ人の悲劇
古代からローマ帝国による離散、中世の迫害、ナチスのホロコースト(600万人虐殺)など
長い流浪と迫害の歴史を経て、安住の地を求めてイスラエル建国を悲願としました。
・パレスチナ人の悲劇
1948年のイスラエル建国に伴い、多くのパレスチナ人が故郷を追われ難民化しました。
彼らはこれを「ナクバ(大惨事)」と呼んでいます。
ユダヤ人が長い迫害の末に故郷を求めた結果、
パレスチナ人が故郷を失うという悲劇的な構造が、
パレスチナ問題の本質なのです。
つまり、故郷問題。
イスラエル(ユダヤ人)にとっては
『ようやく手に入れた祖国』
パレスチナ人にとっては
『元々の故郷』
ということである。
○聖地 エルサレム
キリスト教(God)、ユダヤ教(ヤハウェ)、イスラム教(アッラー)は
「同じ神」を信じています。
違いは、神の言葉を授かった人物にあります。
・キリスト教:イエス・キリスト
・ユダヤ教:モーセ
・イスラム教:ムハンマド
エレサレムは、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教
三大一神教の聖地で、凄く重要な都市。
エルサレムは…
ユダヤ人にとっては、古代の歴史的故郷と宗教の中心地
パレスチナのイスラム教徒にとっても、非常に神聖な都市。
めちゃくちゃ複雑ですよね💦
○地続きの恐怖
私たち日本人には理解しにくいのが、領土問題の深刻さです。
日本は島国で、他の国と必ず海を隔てています。
しかし、世界の多くの国々は地続きで存在しており、
国境といっても目に見える線があるわけではありません。
想像してみてください。
もしお隣さんの家と家がくっついていて、行き来出来る状態だったとして…
いつでも誰かが入ってこられる状態
これとんでもなく不安ですよね?
地続きの国境を持つ国々の人々は、常にそのような不安を抱えているのです。
○相互の被害者意識と感情
この紛争の特徴的な点は、双方が被害者意識を持っていることです。
私たちもそうですが、「自分が加害者」と思って行動する人はいません。
「攻撃は最大の防御」という言葉があるように、
自分たちを守るために攻撃することもよくある話です。
この問題には、理性だけでなく深い感情も入り込んでいます。
・家族を失った悲しみ
・故郷を奪われた怒り
・将来への不安
・世代を超えて受け継がれる憎しみ
こうした感情は論理的な議論だけでは解決できない複雑さを生んでいます。
○その他の要因
その他にも様々な要因があります。
そして、これらがこの問題をさらに複雑にしているんです。
・水資源問題
御存知の通り、水は生命線。中東の乾燥地帯では、まさに生命線。
私たちが当たり前に使っている水道水も、この地域では貴重な資源です。
・経済格差
ガザ地区の封鎖による深刻な経済困窮
・国際政治
アメリカ、イラン、EU諸国など多くの国の利害関係
・世代間の意識の違い
戦争体験世代と封鎖下で育った若い世代
・情報戦
SNSの普及による情報の混乱
「世界で最も解決が難しい紛争」と言われる一端が見えてきましたね。
▼「正義」について考える
この問題を考える上で避けて通れないのが「正義」という概念です。
しかし、正義は脆くて、曖昧なものです。
イスラエル側にもパレスチナ側にも、それぞれの正義があります。
大切なのは、一つの説にこだわりすぎて他者を全否定しないことです。
どちらか一方が完全に正しく、
他方が完全に間違っているという単純な話ではありません。
判断する必要はありません。
まずはフラットに知ることです✊
▼「わからない」という態度の大切さ
この複雑な問題に対して、「自分には分からない」と正直に認めることも重要です。
「わからない」「知らない」ことを受け入れることは、
知ろうとすることと同じくらい大切です。
すべてを理解しなければ発言してはいけないということはありません。
大切なのは、この問題を他人事として片付けるのではなく、
わからないこと・知らないを受け入れ、知ろうとすること。
そして、私たち一人一人が考え続けることです。
▼ 私たちは知らないうちに戦争に関わっているかもしれない
ニュースやこうやって文章で見るだけでは、本当に他人事ですよね。
正直、私も他人事でした。
だけど、ガイドさんの話を聞いて、
「自分も加担しているのかも…」
と思ってしまいました。
・武器産業の現実
世界最大の武器輸出国はアメリカで、
イスラエルへの武器供給の約7割を担っています。
ロシア、フランス、ドイツ、イギリスなども主要な武器輸出国です。
日本にも軍需企業は存在します。
三菱重工業や川崎重工業などの大手企業が
・戦闘機
・ミサイル
・戦車
・潜水艦用機器
などを手掛けており、防衛予算拡大に伴い防衛部門の売り上げも急増しています。
▼私たちの消費行動
何が言いたいかといいますと…
私たちが日常的に購入している商品が、
間接的にこうした争いに関わっている可能性もあります。
※あくまで可能性です!
例えば、武器を作っている国の製品を買うことで、
それが回り回って、武器産業に回っているかもしれません。
法的に言えば、
「一般商品を買ったからといって戦争に直接加担している」
とは言えません。
が、「消費や投資は、その企業のあらゆる事業活動(軍需・武器生産)を間接的に支える」
という社会的・倫理的つながりも存在します。
例えば、S&P500にもそういった企業も含まれています。
こんな感じで、完全に避けることは難しいですが、
知ること、意識することはできます。
▼私たちにできること
では私達に何が出来るのか?
①知ることから始める
まずは、こうした問題があることを知ることが大切です。
無関心が最も良くないのではないでしょうか。
②学び、考え、話し合う
ガイドさんが話してくれたように、
一人で考えるだけでなく、家族や友人と話し合ってみることも大切です。
様々な視点から問題を見ることで、より深い理解につながります。
③消費者としての選択を意識する
エシカル商品の選択:フェアトレード商品や持続可能な製品を選ぶ
日本製品の支援:国内経済を支えることで、平和的な社会づくりに貢献する
情報収集:企業の社会的責任について調べてみる
先日、私は
「最近、日本製の製品を意識的に買っている」
書きました。
その時にはこのような問題は頭になかったのですが…
多少高くても良い選択だなと思いました。
※一般消費財(食料品、衣料品、家電など)の多くは軍事産業とは無関係です。
日本製品を選ぶことで、平和を重視する姿勢を示すことができるかもしれません。
▼というわけで
パレスチナ問題は、宗教、領土、歴史、経済、国際政治、そして深い感情など
様々な要因が複雑に絡み合った問題です。
私たちができることは、
・関心を持ち続けること
・学び続けること
・話し合うこと
そして
・日常の選択を意識すること
です。
「わからない」ことを認めながらも、
知ること・考えることを止めてはいけません。
完璧な答えなんてないし、そんなものを見つける必要はありません。
大切なのは、この問題を他人事として片付けるのではなく、
私たち一人一人が考え続けることです。
平和は決して当たり前ではありません。
話を聞いて、そして、自分で調べてみて強くそう思いました。
━━━━━━━━━━━━━━
今日のコメントテーマは
【最近買った日本製のもの】
です。
皆さんは最近、日本製のものを買いましたか?
ちなみに私は、キャップと爪切りを買いました🧢
皆さんが最近買った日本製のものを教えて下さい!
今日もありがとうございました🙇♂
また明日!
お父ちゃんでした👋
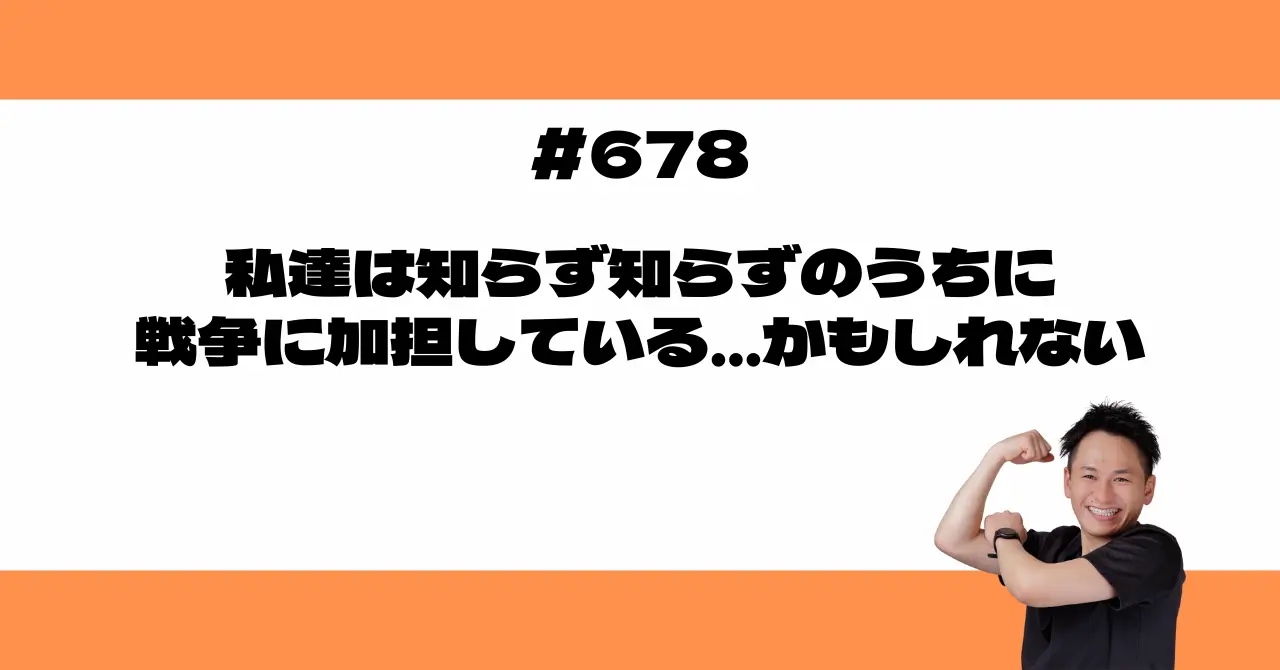


コメント