おはようございます☀
お父ちゃんです!
▼映画『フロントライン』が投げかける「問い」
先日、映画「フロントライン」観ました。

日本中が固唾をのんで見守ったダイヤモンド・プリンセス号での集団感染。
その最前線で闘ったDMAT(災害派遣医療チーム)や関係者の姿を描いた
ドキュメンタリー映画です。
観終わった直後、私の心に残ったのは
単純な感動や称賛ではありませんでした。
むしろ、ずっしりと重い「問い」の数々。
☑️ メディアが映し出す物語はただの一側面
☑️ 光と影
☑️ 情報とどう向き合うべきか
この映画は、現代社会を生きる私たち一人ひとりに、
静かに、しかし鋭く語りかけてきます。
▼「遅さ」が伝えるもの
ちなみに、これは私の勘違いかもしれませんが、
映画全体が意図的に「遅く」感じられました。
普段から動画や音声を倍速以上で視聴することに慣れてしまったせいか、
登場人物のセリフや一つひとつの動作が、
とにかくゆっくりに進んでいくように思えたのです😅
(これは現代病です💦)
それとも意図的なものだったのか…
☑️ 当事者たちが感じていた息の詰まるような時間の流れの追体験
☑️ 極限状況の「緊張感」を伝えるため
☑️ 「丁寧に伝えたい」という想いの表れ
はたまた、私が倍速に慣れすぎている😅
▼スポットライトの死角にいる人々
この映画を観て最初に感じたのは、私たちが普段、
いかに「物語の主人公」しか見ていないか、ということでした。
当時、メディアの主役は間違いなく「感染した乗客」でした。
恐らく、まだまだ危機感とかもなく、
映画では視聴率を稼ぐために煽っているような描写もありました。
(実際そうだった!!)
彼らの不安や恐怖が連日報じられ、多くの人々が心を寄せました。
しかし、その裏側では、膨大な数の人々が事態の収拾に奔走していました。
☑️ 不眠不休で治療にあたるDMAT隊員
☑️ 乗客の生活を支える船のクルー
☑️ 前例のない判断を迫られる厚生労働省の職員たち
映画は彼らの奮闘を映し出しますが、私の思考はさらにその先に及びました。
「この人たちの心配は、一体誰がするのだろう?」
彼らにも帰りを待つ家族がいます。
自分の家族が危険な現場へ向かうことへの不安、世間からの心ない偏見。
そして、それは単なる杞憂ではありませんでした。
実際に、DMATだけでなく多くの医療従事者やその家族が、
筆舌に尽くしがたい差別に苦しんだと聞きます。
☑️ 子供が学校や保育所で隔離されたり、登園拒否
☑️ 日常のサービスの提供を断られる
☑️ 家族が職場で不当な扱いを受ける
☑️ 親戚や地域社会からの孤立
しかもメディアは、DMATと叩くことさえあったとか…
あまりにも残酷な仕打ちですよね。
光が強ければ強いほど、その影は濃くなる。
私たちは、その影の部分にこそ目を凝らす必要があるのです。
▼日本の「強さ」と「弱さ」
この一件は、奇しくも日本の社会や組織が持つ二つの側面を浮き彫りにしました。
一つは、紛れもない「強さ」。
それは、現場に立つ一人ひとりの『使命感』と、
自らの職務を全うしようとするプロフェッショナルな姿勢です。
そして、もう一つが構造的な「弱さ」。
「いったい、誰が責任を取るのか?」
その問いの前で、決断は先延ばしにされ、時間は刻一刻と過ぎていきます。
このもどかしいほどのコントラストを象徴していたのが、
窪塚洋介さん演じるDMAT隊員の仙道と、
小栗旬さん演じる結城の二人でした。
現場の惨状を前に突き進もうとする仙道(船内)と、
政治や前例に縛られながらも奔走する結城(船外)。
そこには凄まじい「中と外の温度差」が存在します。
しかし、立場の違いから激しく衝突しながらも、
彼らが心の底で「一人でも多くの命を救いたい」という
同じ目的地を目指していたことは明らかでした。
▼情報との向き合い方
もし自分がDMAT隊員としてあの現場にいたら、
外野から無責任な批評を繰り返す人々に
「何も知らないくせに」と、きっと感情的になったでしょう。
そう思った時、自分自身の過去がよみがえります。
私自身、コロナ禍の混乱の中で、不確かな情報を鵜呑みにし、
その情報を誰かに話してしまった経験があります。
その反省があるからこそ、痛感することがあります。
それは、「一次情報」に触れることの重要性。
そして、それ以上に大切なのが、
「自分には分からない」と正直に認め、「保留する」という態度です。
情報が溢れる現代では、つい何にでも白黒をつけ、自分の意見を表明したくなります。
しかし、現場に立つ人々の声を聞くまでは、
その複雑な現実を知るまでは、
軽々しく「ああだこうだ」と言うべきではないと私は改めて思いました。
分からないことを分からないままにしておく。
それは無知なのではなく、
むしろ物事の複雑さに対する誠実さと敬意の表れではないでしょうか。
▼私なりの「情報との付き合い方」
私は最近、情報との付き合い方を変えています。
まず、テレビのニュースや大手ニュースサイトを、ほとんど見ない。
それは、無意識のうちに「偏った情報」を浴び続けないための、自分なりの防衛策です。
ちなみに、誰かが大きな声で何かを訴えている時、
真相はその裏側にあったりします。
SNS(インスタやFacebook)は使用するけど、
情報収集には使っていません。
それらを見ない代わりに、AIなどのツールを使い、
「このジャンルの情報を集めてほしい」と
能動的に情報を取得するようにしています。
本当に重要なニュースであれば、わざわざ取りに行かなくても、
信頼できる誰かを通じて自然と耳に入ってくる、という確信もあります。
これは情報化社会における、一つのサバイバル術なのかもしれません。
しょうもないニュースに、時間や精神を奪われている場合じゃありませんからね!
▼「感動」から「問い」へ
映画「フロントライン」は、
私に安易な「感動」を与えはしませんでした。
その代わり、自分の頭で考え、社会を多角的に見つめ、
自分自身の在り方を問い直すための、数多くの「問い」をくれました。
私たちはこれからも、正解のない問題に直面し続けるでしょう。
その時、大切になるのは、たった一つの答えを急いで見つけることではありません。
無数の「問い」を抱えながら、それでも『考え続ける力』ではないでしょうか。
窪塚洋介さんが凄く良い味を出していましたね〜😊
━━━━━━━━━━━━━━
本日のコメントテーマは
【最近見た映画】
です。
皆さんが最近見た映画があれば、教えて下さい!
私は、Netflixの「TITAN」という映画も見ました🎞️
これも経営者として考えさせられる映画でしたね🤔
その話はまた!
今日もありがとうございました🙇♂
また明日!
お父ちゃんでした👋

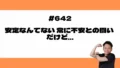

コメント