おはようございます☀
お父ちゃんです!
Netflixが絶好調です。
2025年第2四半期(4~6月期)の売上高は
前年同期比16%増の約1兆6,500億円(110億7,900万ドル)を記録
収益・利益で過去最高を更新しました。
2025年6月には『有料会員数が3億人を突破』という歴史的な節目を迎えています。
この好調さの要因として、広告付きプランの導入と数々のヒット作品の存在があります。
特に「イカゲーム」シリーズの新シーズンは
短期間で7,200万回超えの再生数を記録し、改めてその影響力を見せつけました。
私は最近「イカゲーム」を視聴しました。
同じくヒットドラマの「ペーパー・ハウス」も見たが、こちらは途中で断念。
そして9月には山崎賢人、土屋太鳳出演の「今際の国のアリス」の新シリーズが配信されます。
これら3作品を比較して気づいたのは、
なぜこれらの作品がグローバルでヒットするのかという共通点。
今回は、これらの作品のヒットの共通点を私なりに分析してみました。
▼ ゲーム性の心理学的メカニズム
「イカゲーム」の「だるまさんがころんだ」や「綱引き」、
「今際の国のアリス」の「かくれんぼ」やトランプゲームが、
なぜこれほど視聴者を惹きつけるのか?
「残酷すぎる成功法則」によると、面白いことに含まれる共通要素として、
①勝てること: 勝算が見込める自分なりのゲームを決め、それに取り組む
②斬新であること: 人間の脳はたえず斬新さを求める
③目標: 目標はプレッシャーや脅威にもなりうるが、勝算が見込める形でゲームを定めれば、目標は脅威でなくなる
④フィードバック: 定期的に尋ね、フィードバックをもらう
「イカゲーム」の各ゲームは、まさにこの4要素を完璧に満たしています。
誰もが知っているルールだから「勝てる」と感じられ、
命をかけるという設定で「斬新」さを演出し、
明確な「目標」(生存・賞金獲得)があり、
即座に生死という「フィードバック」が得られる。
この心理学的な仕組みこそが、
単純なゲームを極上のエンターテインメントに変える秘密です。
▼ 一発逆転への憧れの不合理性
イカゲーム、ペーパー・ハウスに見られるのは、一発逆転である。
イカゲームの参加者は、多額の借金を抱えている。
ペーパー・ハウスのチームメンバーは、過去に犯罪を犯したことのある者たちで構成されている。
人間は一発逆転に憧れがあるのだ。
「予想通りに不合理」に、人間の不合理な性質が書かれています。
☑️「人に何かを欲しがらせるには、簡単に手に入らないようにする」
☑️「人は持てば持つほど一層欲しくなる」
☑️ 「無料だと、欲しいものがあってもそっちを選ぶ」
「イカゲーム」の参加者たちが巨額の賞金に惹かれるのも、
この心理メカニズムが働いているからではないだろうか。
賞金は「簡単に手に入らない」からこそ、より強く欲しくなる。
そして一度ゲームに参加すると、『所有意識』が働き、
途中で諦めることが困難になります。
宝くじが人々を魅了し続けるのも、
借金を抱えた人が一発逆転を夢見るのも、
すべて同じ心理的メカニズムです。
現実的には割に合わないと分かっていても、
人は一発逆転の可能性に賭けてしまう。
これは人間の本能的な性質なのです。
あなたにも一発逆転への憧れ、ありませんか?
▼ 極限状況での人間性
「人は追い込まれると、本性が出る」
とよく言います。
イカゲームも、ペーパー・ハウスも、今際の国のアリスも
極限状態で様々な判断を下していきます。
極限状況に追い込まれた時の
・人間の選択
・友情と裏切り
・生存をかけた戦い
これらは万国共通の普遍的テーマです。
「今際の国のアリス」が日本発の作品として世界的にヒットしているのも、この文脈で理解できます。
カイジなんかも、同じような手法が使われていますよね!
日本の漫画文化が長年培ってきた「極限状況での人間ドラマ」の手法が、
グローバルな舞台で花開いているのです。
▼ 人間ドラマが生む感情移入
これらの作品に共通するのは、単なるゲームやアクションではなく、
一人一人に背景があって、人間臭さ、人間らしさが垣間見えることです。
極限状況に置かれた時、人はどんな選択をするのか。
仲間を裏切るのか、それとも自分を犠牲にするのか。
登場人物たちの過去の経験や価値観が、その選択に大きく影響します。
だからこそ、視聴者は感情移入し、ハマっていくのだと思います。
「ペーパー・ハウス」を途中で断念したのは、
おそらくゲーム性よりも政治的・社会的メッセージが
前面に出すぎていたからかもしれません。
「イカゲーム」や「今際の国のアリス」の方が、
より純粋にゲーム性と人間ドラマに焦点を当てている印象がありました。
あと、逃走中(鬼ごっこ)もこれに近いものがあると思ったのですが、
Netflixではドラマ部分が少なかったり、鬼ごっこだけで一本はなかなか大変なのかなと。
私達がテレビで見る分には、出演している方(日本の著名人)が
・何をしている人で
・どんな人か
などをある程度知っているから、日本ではウケたけど、
Netflixのようなところではハマらなかったのかなと…
▼ ということで
これが私の分析して出した仮説です。
・誰もが知っているゲーム
・極限状況で人間ドラマ
・一発逆転への憧れ
韓国発の「イカゲーム」
スペイン発の「ペーパー・ハウス」
日本発の「今際の国のアリス」
これらがすべて世界的にヒットしているのは、
まさにこれらの心理学的な普遍性があるからなのかなと。
9月に配信される「今際の国のアリス」シーズン3も、
おそらく同じ法則でヒットすると思います。
「イカゲーム」のヒットは決して偶然ではありません。
人間の根深い心理的欲求と、普遍的な物語の構造を見事に組み合わせた結果なのかなと。
出典元:カモのネギには毒がある 11巻
出版社:集英社
著者名:甲斐谷忍
私たちがこれらのドラマに惹かれるのは、
そこに自分自身の欲望や憧れ、そして人間としての本質を見出すからかもしれません。
現実では味わいたくない物語。
まさにエンタメですね!
━━━━━━━━━━━━━━
今日のコメントテーマは
【九死に一生を得た経験】
です。
イカゲームも、今際の国のアリスも
脱落者は○されるんですね。
皆さんは、九死に一生を得た経験はありますか?
もしあれば教えて下さい‼️
私は今のところ…
ありません🤔
今日もありがとうございました🙇♂
また明日!
お父ちゃんでした👋
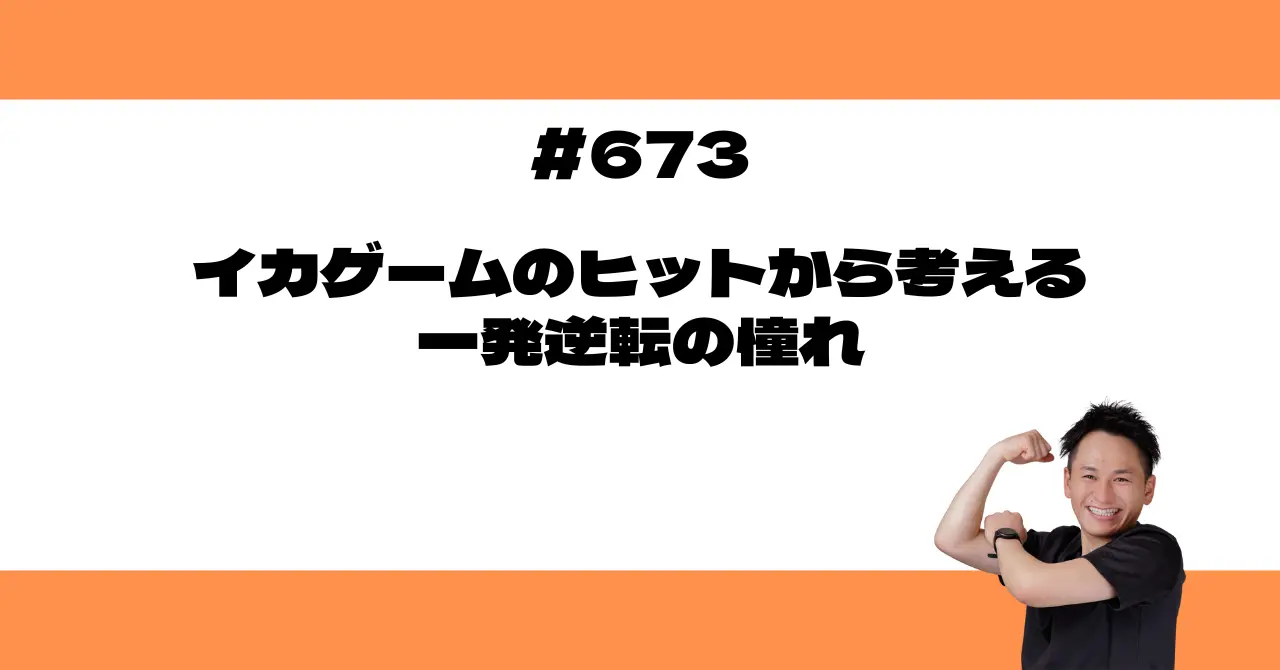
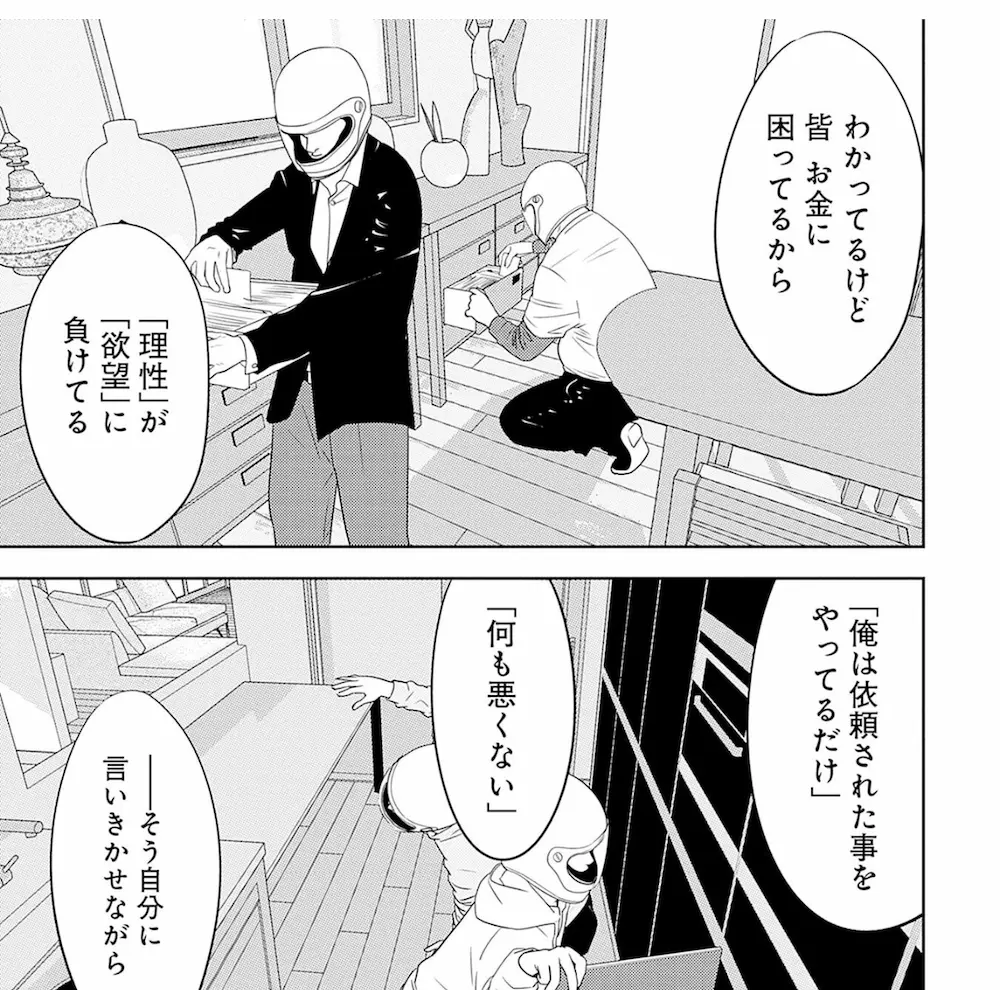
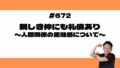

コメント