おはようございます☀
お父ちゃんです!
先日、妻が夜中に泣きながら私を起こしてきました。
👩「Gが出た😭😭😭」
と…
25時頃に起こされた私は妻が奴らを見た場所に行き、
退治して、布団に戻りました。
その時間、約三分⏰️
ゴキブリ――通称「G」。
その姿を見ただけで、思わず声を上げてしまう人も少なくないでしょう。
しかし、この生き物はただの”嫌われ者”ではありません。
実は、約3億年以上前にその祖先が地球上に登場し、人類の歴史をはるかに凌ぐ長い時間を生き延びてきた、まさに「生きる古代生物」なのです。
▼ゴキブリは本当に”害虫”なのか?
地球上には3500〜4000種以上のゴキブリが報告されています。
ところが、私たちが日常生活で目にする”害虫”とされる種類は、全体のわずか1%未満です。
残りの99%以上は、熱帯・亜熱帯の森林を中心に暮らし、生態系の中で重要な役割を果たしています。
その役割が「分解者」
彼らは朽ち木や落ち葉といった腐敗した植物を食べ、それらを分解して土壌に栄養を戻します。
もし彼らがいなければ、森林の物質循環は滞り、生態系全体の健全性が損なわれてしまう可能性があります。
つまり、「害虫」というラベルはゴキブリ本来の性質ではなく、人間視点から貼られたレッテルにすぎないんです。
(何て勝手な人間様!)
▼”豊かさの象徴”から嫌われ者へ
今では想像もつきませんが、昔の日本では一部の地域でゴキブリは「豊かな家の証」とされていました。
とうのも、高度経済成長期以前の日本家屋は保湿性が低く、冬はとても寒く、食料も潤沢ではありませんでした。
そのため、寒さが苦手なゴキブリが冬を越せるのは、常に暖かく、食料の余剰がある裕福な家に限られていたからです。
そんな豊かさの象徴でも合ったゴキブリが、なぜ忌み嫌われる存在となったのか?
ゴキブリが一気に忌み嫌われる存在になったのは、日本の高度経済成長期。
1960年代以降、住宅は気密性が高まり、冬でも室内が暖かく保たれるようになりました。
これはゴキブリにとって理想的な繁殖環境。
加えて台所や食品庫には食料の余剰が生まれ、彼らの生存条件は一気に整いました。
結果、個体数は爆発的に増加し、人間との遭遇率も跳ね上がります。
そこへ登場したのが、家庭用殺虫剤。
1960年代後半からテレビCMが放映され、ゴキブリは「家庭の敵」として明確に位置づけられました。
CMのインパクトは絶大で、恐怖や嫌悪のイメージは社会全体に急速に定着していったのです。
▼ゴキブリが嫌われる3つの理由
では、なぜ私たちはこれほどまでにゴキブリを嫌うのでしょうか?
私の考える理由は次の3つです。
1.黒光りする見た目
特に夜間、光を反射するあの黒さは、直感的に「不気味」と感じさせます。
黒さだけならカブトムシやクワガタのメスも似ていますが、ゴキブリの場合は別の要素が加わります。
2.不意に現れること
日中は姿を見せず、夜、部屋の電気をつけた瞬間に突然出てくる。
予測不能な出現は、人間の恐怖反応を引き起こします。
3.圧倒的なスピード
ゴキブリの素早い動きは、視覚的にも心理的にも不快感を増幅させます。
カブトムシやクワガタは遅いので、同じ黒さでも恐怖を感じにくいのです。
▼嫌悪感は”本能+文化”でできている
ゴキブリ嫌いは、単なる衛生的懸念だけでなく、本能的な警戒心と、メディアによって強化された文化的イメージの組み合わせです。
予測不能な速い動き、暗闇からの突然の出現は、私たちの脳が「危険!」と即座に判断する条件と一致します。
そこにテレビCMや広告が加わり、「ゴキブリ=悪役」という物語が完成したのです。
病原菌の運び屋でもあるゴキブリ。
実は、彼ら自身は本来、非常に清潔好きで、自身の体表からフェノールやクレゾールといった殺菌作用のある物質を分泌しているという報告もあります。
なので、ゴキブリが本質的に不潔なのではなく、
『そういった環境でも生き延びられるように進化した』
ということです。
▼ということで
そろそろ辞めましょうか😅
ゴキブリの歴史、そして、豊かさの象徴から嫌われ者への転落の物語。
いかがだったでしょうか?
ちなみに私は、妻に起こされた後、気持ち悪さ…
からではなく、この考えをブログにしようと考えていたら寝られなくなってしまいました🤣
私を起こした妻のほうが先に寝ていました🤣
今日もありがとうございました🙇♂
また明日!
お父ちゃんでした👋
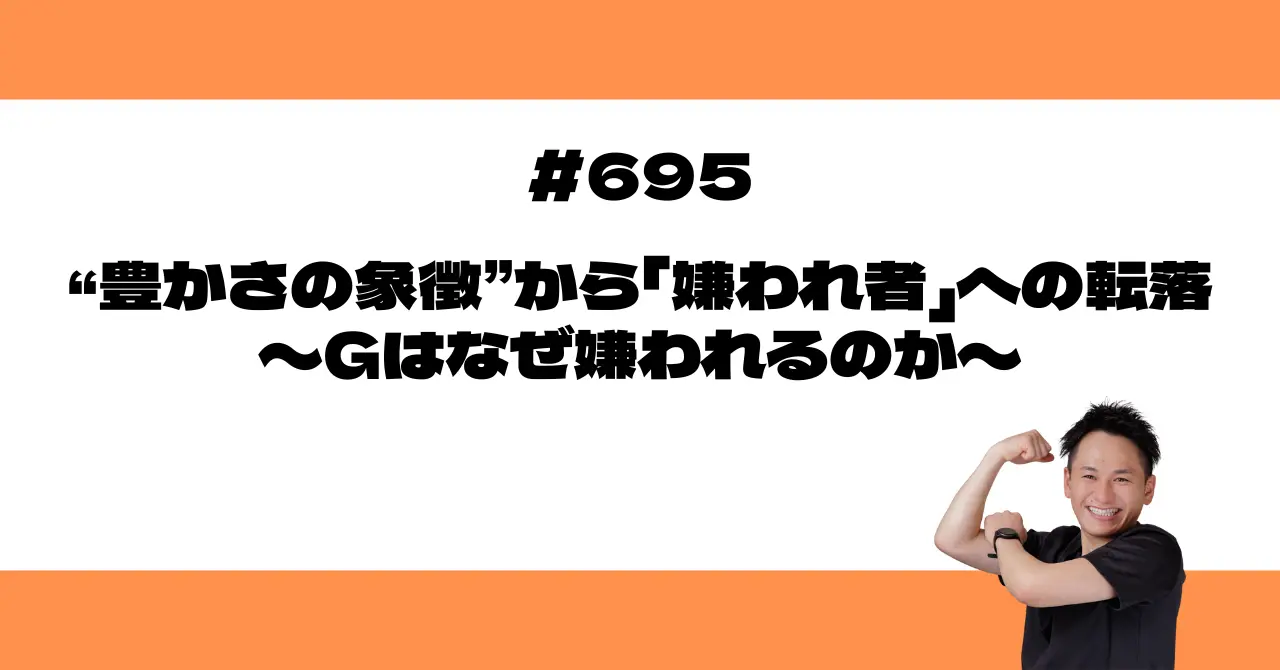


コメント