おはようございます☀
お父ちゃんです!
先日、6月の大阪万博・キルギス共和国のナショナルデーに続き、
パプアニューギニアのナショナルデーにも参加させていただきました。

今回も現地パフォーマーの施術を担当するためです。
キルギスは中央アジアに位置するため、日本人と体の感じは比較的似ていました。
しかし、パプアニューギニアの方々は明らかに体の作りが違った。
とにかく筋肉がゴツい💪
体全体がゴツいというよりも、筋肉がゴツい💪

筋肉がゴツいというと、激しいトレーニングを積んでいるように思うかもしれません。
もちろんそういった方もいるでしょうが、
聞くところによるとこれは生まれ持っての体質、筋肉のゴツさだそうです。
▼ 60年以上続く「栄養学的パラドックス」の謎
科学の世界には、長年にわたり研究者の知的好奇心を刺激し続ける謎が存在します。
パプアニューギニア(PNG)高地の人々が提示する
「栄養学的パラドックス」は、その典型例です。
標高1500から2000メートルの山岳地帯に暮らす彼らは、
サツマイモを主食とする食生活を送っています。
この食事は、現代栄養学の基準から見れば
著しくタンパク質が不足しているにもかかわらず、
高地の人々、特に成人男性は、脂肪が少なく筋骨隆々とした強靭な肉体を維持しています。
私達の常識として、
「体を作るには、筋肉をつけるにはタンパク質が必要」
というものがありますよね?
だけど、彼らは圧倒的にタンパク質摂取量が少ないんです。
それでも脂肪が少なく筋骨隆々とした強靭な肉体を維持している。
この研究は60年以上前から続けられているが、未だ完全には解明されていません。
▼ タンパク質についての新たな視点
ここで現代栄養学の常識を覆す重要な事実を考えてみましょう。
「Switch オートファジーで手に入れる究極の健康寿命」という本に
”現代人はすでに必要量のたんぱく質を摂取できている”
”むしろ厄介なのは、タンパク質の過剰摂取のほう”
と書かれています。
この視点に立てば、パプアニューギニア高地民の謎は全く違って見えてきます。
私たちが「タンパク質不足」と考えている状態は、
実は人類本来の適応能力を発揮できる理想的な状態なのかもしれません。
▼体の再利用システム
「Switch オートファジーで手に入れる究極の健康寿命」には、こうも書かれています。
”タンパク質の供給が減ると、身体はあらゆる手段を使って既存のタンパク質を再利用しようとする”
これはまさに、パプアニューギニア高地民の体内で起きている現象そのものを表現しているのではないでしょうか。
現在のところ、彼らの体では、以下のようなメカニズムが働いていると考えられています。
① 遺伝的要因
高地でタンパク質をあまり摂取できない環境でも生き抜いていけるよう、
長い時間をかけて適応進化してきた。
②腸内細菌による窒素固定
腸内の気体である窒素ガスをアンモニアに変換して、
それをアミノ酸合成に利用する仕組みが発達している。
③尿素窒素の再利用
タンパク質代謝の最終産物である尿素が尿として排出されずに腸管へ移行し、
腸内細菌によってアンモニアに分解され、新たなアミノ酸合成の材料として再利用。
これらは現代で言う「オートファジー」や「タンパク質の再利用システム」が、
極限まで発達した状態と考えることが出来ます。
糖新生が糖不足時に他の物質からエネルギーを作り出すように、
彼らの体内では限られたタンパク質を最大限活用するシステムが構築されているのです。
体は生きるためにどうにかこうにかしていくって感じですね‼️
▼身体活動量も大きな要因
また、彼らの生活様式も重要な要因として忘れてはいけません。
農作業が多かったり、
険しい山岳地帯での移動が日常的だったりと、
運動量が非常に多いのだ。
高地であること、この高い身体活動量も、
筋骨隆々とした体型の維持に大きく貢献していると考えられます。
▼進化は続いている
パプアニューギニア高地民の体質は、
彼らの環境と生活様式に完璧に適応した結果です。
現代栄養学の「一律の基準」では測れない、
個体差と環境適応の素晴らしい例と言えます。
人間もまだまだ進化の過程にあるのだなと…
パンダが竹を主食とするよう進化したように、
パプアニューギニア高地民の体質は、環境への適応という進化の一例です。
これはパプアニューギニア高地民に限らず、我々もそうです。
人間・動物・植物などすべてにおいて進化途中で、
何百年、何千年先には、また違う形で進化しているかもしれません。
これからも環境に適応し、生きていくために、非常に長い時間スケールの中で
相互に作用し合ってバランスを取り合いながら進化していくのかなと…
▼現代化がもたらす新たな課題
しかし最近、彼らの健康に予期せぬ影響が出始めています。
それは食事の欧米化です。
これまでの伝統的な食事から加工食品に変わったり、
簡単にタンパク質や糖が摂取できるようになったりしています。
ナショナルデーの控室でも、551の豚まんを一気に4つくらい食べている人も😅
もともと「適度なタンパク質摂取」に適応した体質に、
高タンパク・高糖質の食事が加わると、体はより大きくなっていきます。
その結果、肥満や生活習慣病が問題となってきています。
長い時間をかけて築かれた生理学的バランスが、急激な環境変化によって崩れてしまう。
便利になる・世界がつながることの弊害でもありますね。
▼というわけで
実際に様々な国の方々の身体に触れて施術することで、
教科書では学べない発見が多くあります。
日本人同士でも一人一人違うし、アジア人同士でも一人一人違います。
しかし地域が異なる方との身体的なコミュニケーションを通じて、
人類の多様性をより深く実感出来ました。
一概に人間といっても、本当にいろんな方がいます。
それぞれが長い歴史の中で環境に適応してきた結果としての、
かけがえのない多様性です。
まだまだ分かっていないことも多いですが、
「人間が今もなお時間をかけて進化し続けているのだ」ということを、
パプアニューギニアの方々の身体を通じて実感した貴重な体験となりました。
私達は
「〇〇をすれば正解」
みたいなのを欲しますが、そんなものはありません。
一人ひとりの体質と個体差があります。
結局自分で見つけるしかありません。
その大切さを、改めて教えてくれた出会いでもありました。
人体って面白いですね🎶
今回も楽しかった🎶
みんな明るく陽気で、フレンドリー!
控室でも、みんなで歌ったりしてましたからね😆

━━━━━━━━━━━━━━
今日のコメントテーマは
【人体の不思議】
です。
最後にも書きましたが、人体って本当に不思議です。
昔、人体の不思議展というのがあって…
あれ、もう一回やってほしいな🎶
皆さんが「人体って不思議」と感じたことがあれば
コメント欄で教えて下さい!
私は仕事柄、人の体をよく見るし、触るのですが…
痛みについて!
例えば…
骨に変形があるからと言って、痛みが出るわけではないんですね。
痛みは過去の出来事とか、これまでの経験とかが
かなり関わっているそう!
だから、なかなか取れない痛みを取ろうと思うと、
外部からの治療だけでなく、内面からほぐしていく必要があるんです。
今日もありがとうございました🙇♂
また明日!
お父ちゃんでした👋


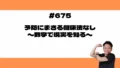
コメント